| 五行の法則 |
| 作成日平成17年6月13日 |
| 木気 | 陽遁の生成発展・陰遁の衰退の働き
|
|||||
| 火気 | 陽遁の成熟・陰遁の消滅の働き
|
|||||
| 金気 | 陽遁の衰退・陰遁の生成発展の働き
|
|||||
| 水気 | 陰遁の成熟・陽遁の消滅の働き
|
|||||
| 万物はすべて、時間(四気)と場(土気)の中におかれている (万物は場の中にあって、場の影響を受け、それにとって働きや性格を規定されている) =「万物は場によって創られている」 |
||||||
| 土気 | 木火金水の四気が形を取るための素材を提供する
|
|||||
| 五行の相生相剋 |
| 作成日平成17年7月12日 |
| 簡単に自然現象に譬えて説明するとすれば | ||
| 「相生」とは、 | 「相剋」とは、 | |
「木は火を生じ、火は土(灰)を生じ、土中からは金(鉱石等)が生じ、金(岩)から水が生じ、水は木を生じ育成する」 |
「木は根を張って土を剋し、土は堤防となって水を剋し防ぎ、水は火を剋して消し、火は金を剋して溶かす」 |
|
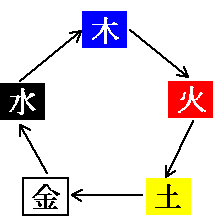 |
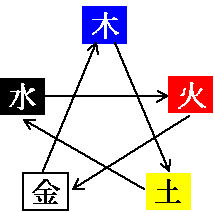 |
|
| ①木生火:「木は火を生ず」 木は燃えて火を発生させます。 これは、火の立場から言えば、火が燃えるのを木が助けてくれることを意味していますし、また、木の立場から言えば、木の持っているエネルギーが火となって外に放出されることを意味しています。 良く取れば木の潜在エネルギーが外に現れて他のものを暖めたり、明るくしたりという貢献をすることでもありますが、木自体からすれば、消耗して自分がエネルギーを失うことでもあります。 |
①木剋土:「木は土を剋す」 木は土中に根を張ることによって、土を押しのけ土の養分を吸収します。 木(植物)が繁茂し過ぎると、土は痩せてしまいます。 逆に、土が強すぎて硬くなっても、木が根をはることが出来ず、木も反剋作用を受けて、枯れてしまいます。 |
|
| ②火生土:「火は土を生ず」 火は燃え尽きれば灰となり土と化します。 また、火は柔らかい土を固めて強固な土(器)としてくれます。 適度な火と土の関係は良質の陶器などを生み出すこともありますが、過度の火と土の関係では、日照りの為に畑が乾いて、作物を育成することが出来ない土となることもあり、土の用途と性質によって、「火生土」も良く働いたり、悪く働いたりします |
②土剋水:「土は水を剋す」 土は堤防となって水が氾濫するのを防ぐ作用をします。 土が強すぎたり、悪い土であると、水は濁ってしまうことになります。 水の勢いが強すぎると、土も反剋作用を受けて、堤防が破れて水が氾濫してしまうこともあります。 |
|
| ③土生金:「土は金を生ず」 土中から金(金銀・鉱石・宝石)などが掘り出される事象に譬えることが出来る関係です。 |
③水剋火:「水は火を剋す」 水は火を剋して消す作用をします。 適当な水は火を抑えてくれ、水も火の反剋作用によって暖められることもありますが、強すぎる水は完全に火を消してしまって、火の効用までもなくしてしまうこともあります。 また、強すぎる火に水を注ぐことによって、却って消すどころか爆発させてしまうことさえもあります。 |
|
| ④金生水:「金は水を生ず」 岩間(金)から水が生じることに譬えられ。 金の側から見ると「金生水」は金の潜在能力を引き出す作用であり。 |
④火剋金:「火は金を剋す」 火は金を剋して金属を熔かし変形させる作用をします。 火の勢いが強すぎれば鋼も完全に熔けてしまいます。 |
|
| ⑤水生木:「水は木を生ず」 水は木を育成する作用に譬えられます。 只、水が多すぎると流木となって木が流されてしまうことになりますので、 適当の水であってこそ木を育成する作用となるものです。 |
⑤金剋木:「金は木を剋す」 金は木を剋し、斧や鋸となって木を伐採します。 木は金によって伐採されて、切り刻まれることによって、人の役に立つ家や家具等の有用の材となることができます。 切り刻まれ過ぎては木は死んでしまい、有用の材となることが出来ません。 木が堅過ぎれば、木の反剋作用を受けて、金(斧や鋸)も折れてしまうことがあります。 |
|
| 陰 陽 | 五行の法則 | 十 干 | |
| 東洋医学の基本的な考え方 |
検索エンジンからの来訪は、ページが古い場合がありますので最新号にはトップページから どうぞ!
| 合気道トップ | テーラーまつき | 峯岸観音 |